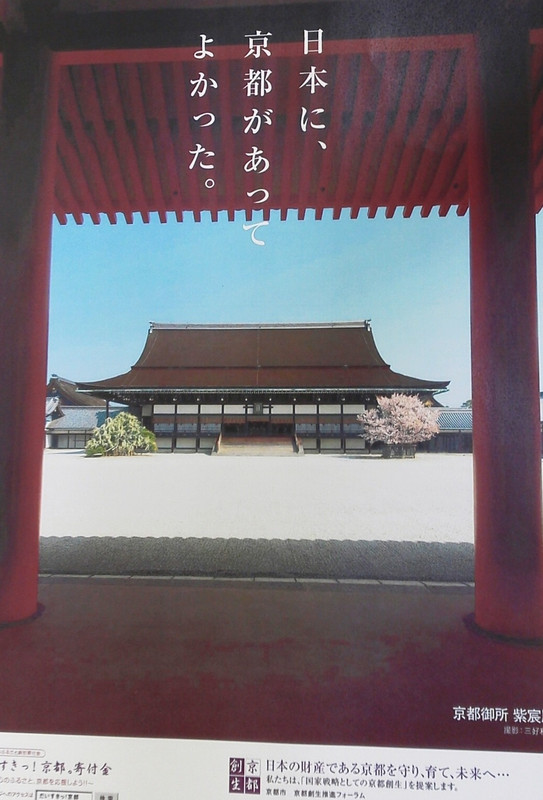3月14日には、経済総務常任委員会に付託された高速鉄道事業基金の廃止等の議案審議の他に、原子力防災計画策定の抜本見直しを求める陳情審査、行財政局からの「技能労務職員の試行的な採用に係わる検証結果」報告、総合企画局からの「京都市公式HP「京都市情報館」のリニューアル方針」、産業観光局からの「新潟市との観光・文化交流宣言」について報告があり、その他一般質問がありました。
技能労務職員の試行的な採用の検証については、平成18年の「信頼回復と再生のための抜本改革大綱」の最終報告案に対する課題、試行的実施の考え方、業務改革の今後の方針などについて質疑がありました。
新潟市との観光・文化交流宣言については、京都市と新潟市が平安時代から経済・文化の往来が盛んである経過、日本酒や花街など共通する分野で多様な文化を育んできた経過、昨年、京都の相国寺承天閣美術館と新潟市の会津八一記念館との間で開催された両市にゆかりのある会津八一の所蔵品交換展の意義、また両市とも東日本大震災で影響を受けている福島県の会津若松市と交流宣言を展開していることもあることなどから、此の程、新潟市と京都市が経済・文化交流を進めることになりました。調印式は、3月26日16時から二条城にて、室井照平会津若松市長等が立会のもとに、門川大作京都市長と篠田昭新潟市長が行なわれる予定です。
私は、一般質問で、補助金適正化条例に関連して京都市職員厚生会について、質疑を行いました。職員に対する厚生制度は、地方公務員法第42条に規定されています。また、同43条には、共済制度として規定されています。しかし今求められているのは、同41条にある「職員の福祉及び利益の保護は、適切でありかつ公正でなければならない」という公僕の立場にある公務員の姿勢にあります。
私は、予算委員会分科会での質疑を踏まえ、「厚生会への補助金交付は、京都市補助金適正化条例の対象である」との見解であったものが、市長総括(1日目)では、「職員厚生会条例」に準拠して補助金を交付している」との見解を示し、さらに2日目の市長総括では、「交付金である」との見解を示すなど、厚生会への補助金の定義が極めて曖昧さを残すものとなっていることを指摘しました。
本日の委員会で、改めて確認したところ、「補助金」であることが明確になり、改めて今回の厚生会への補助金交付は、改正職員厚生会条例(案)を準拠になることが確認されました。一般財団法人として独立化する厚生会への補助金交付については、少なくとも今回から、除外規定にせず、少なくとも交付の①目的、②補助事業の明確化、③補助事業の交付の対象者の明確化、④補助事業の額の算定方法(以上補助金適正化条例 第6条規定)や、同7条の検証、さらには公表義務等を規定している補助金適正化条例に準拠すべきだと考えます。一般会計からの補助金交付は、厚生会の改革内容を検証した上で、交付のための規定整備をするのが望ましいのではないかと思います。
また、理事者からは、「補助金等」の「等」に厚生会への補助金は該当するとの答弁もありましたが、適正化条例の第3条で適用除外されていることに変わりはありません。「等」については他の委員からも「以前の政務調査費のみが該当するとの見解だったのでは」と疑問視する意見も出されました。いずれにしても、改正厚生会条例(案)第3条には明確に補助金と明記されているわけですから、補助金の透明性、妥当性を検証する法的根拠が曖昧であると言わざるを得ません。
今回の改正職員厚生会条例案は、平成25年度から一般財団法人化に伴い、交通局厚生会、上下水道局厚生会の組織を統合廃止する条例であることです。補助金交付とは別の課題だと考えます。そもそも地方公務員法には、「地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹立し、これを実施しなければならない」と、福利厚生の義務を事業者である市長に求めていますが、補助金交付及び給付の中身については明記されていないわけですから、改正厚生会条例は組織の統廃合を目的とする条例のみとし、補助金は任意団体に交付する根拠としている補助金適正化条例に準拠すべきです。その上で、平成25年度からの厚生会事業の廃止、見直しの更なる検討、財政計画の短縮化、事業主負担としての補助金額の縮小に努めるべきではないかと考えます。
情報公開と説明責任は、内部外部を問わずすべての組織に求められている理念と行動指針です。行財政改革、公務員改革、政治改革が問われている今こそ、今回の厚生会の課題を契機に、一層の改革を断行すべき時だと痛感します。