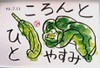抜本改革大綱推進本部会議
続発する京都市職員の不祥事根絶のため過日、桝本市長は改革大綱を発表しましたが、その改革策の進行管理を行う「信頼回復と再生のための抜本改革大綱」推進本部の第一回会議が、9月8日京都市市会9月定例会の召集本会議前に開会されました。
推進本部の本部長である桝本京都市長は会議の中で、4つの指示を行いました。その内容は下記の通りです。
(1)大綱に掲げる改革策を推進する中心的な役割を果たす当該局は、常に進捗状況を把握するとともに、統括本部員である服務監との連携の下、的確に本部長、副本部長に報告し、すべての改革策が要綱にある実施期日に遅れることのないよう、局の総力を挙げて取り組むこと。
(2)大綱の「第三部 全庁的な抜本改革」は、全庁・全分野で取り組む課題であり、すべての所属職員が大綱の推進を自らのこととして捉え、職場単位で、業務遂行に際して、何をなすべきかを徹底的に議論した上で、所属ごとに取組内容・実施時期等を明確にし、それを着実に実施すること。局長等は、その取組事項を取りまとめ、常にその進捗状況を把握するとともに、目標とした実施期限に遅れることがないよう、強く指導すること。名札の100%着用等、服務の基本を徹底すること。
(3)問題や課題を抱えていることが判明した場合には、所属や局区等で情報を共有し、組織的な対応によりその解決を図ること。特定の個人・団体の特別扱いを許すような慣習や組織風土があれば、それを一掃すること。局区長等は、問題や課題があれば、直ちにその原因と対策を取りまとめ、市長、副市長に報告すること。
(4)以上の3点の指示と同時に大切なこととして、それぞれの所属の本来業務について、しっかりと仕事を進め、また、市民サービスを充実していくこと。このことが、市民の皆様の京都市政に対する信頼を回復していく上で最も基本であることを肝に銘じて日々の業務に当たることを強く要請する。