国際幸福デー
昨年の国連決議で、毎年3月20日を「国際幸福デー」と定められました。こうした意義を踏まえ、経済同友会が企画主催され京都府、京都市が連携した催しとして「京都幸福会議2013」が、立命館大学朱雀キャンパスにおいて、盛大に開催され、私も傍聴者の一人として参加させていただ、感銘、感動した一日でした。
会議は、田辺親男京都経済同友会代表幹事の開会のあいさつの後、「ブータンのGNHから、これからの幸福の在り方を考える」と題して、カルマ・ウラ王立ブータン研究所所長、島薗進東京大学大学院人文社会系研究科教授、吉川左紀子京都大学こころの未来研究センター長の3人の特別鼎談が行われ、その後、「幸福が実感できる京都づくりをすすめるためには」と題して、山田啓二京都府知事、門川大作京都市長、田辺親男経済同友会代表幹事のセッションがありました。
ブータン王国は、経済等の国力を示す国民総生産量(GNP)に対して、精神面での豊かさを「値」として示す国民総幸福量(GNH)を率先して国策として進めている国で、世界比較で第一位の座にある国です。ブータンでは2年毎に聞き取り調査を実施し、人口67万人のうち、72項目の分析指標シートに、一人当たり5時間の面談を行い、8000人のデータを集めています。数値化し分析するために、幸福度の指標を9つに分類しています。1.心理的幸福、2.健康、3.教育、4.文化、5.環境、6.コミュニティ、7.良い政治、8.生活水準、9.自分の時間の使い方の9分類です。面白いのは、計測がなかなか困難な「心理的幸福」については、①寛容、②満足、③慈愛、④怒り、⑤不満、⑥嫉妬を、心に抱いた頻度を集め地域的に国民感情を示す幸福地図を作っていることです。
カルマ・ウラ所長からブータンの国民の話がありましたが、ブータン人は、平均89分を食事時間に費やし、79分を祈りの時間に費やし、63分をコミュニティの時間に費やすなど、スローライフの国です。日本人はあまりにもファーストライフに身も心もすり減らしている感があると指摘され、幸福度には、過去・現在・未来の時間軸を踏まえなければならないことも指摘されていました。またカルマ・ウラ所長は、「幸福感を高めるためには、外面のモノ等の充足では足らず、内面の充実感を高めなければならない。内面から発する価値観を高めることが重要であること。幸福は一人では確立できず、全体、集団の中の個人であってはじめて確立できること。仏教国であることから、高い精神性が国民や自然に根付いており、中道の価値観が幸福度を高めている。」等、多くを箴言されていました。
2012年の国連決議の折、事務総長は、「初の「国際幸福デー」にあたり、包摂的で持続可能な人間開発に向けた私たちの決意を新たにするとともに、他者を助けていくことを改めて誓おうではありませんか。共通の利益に貢献すれば、私たち自身が豊かになれます。痛みを分かち合えば、幸福だけでなく、私たちが望む未来も近づいてくるのです。」と語りましたが、まさに、幸福な他者に寄り添い、助けていくことを誓う中にしかないことを痛感しました。

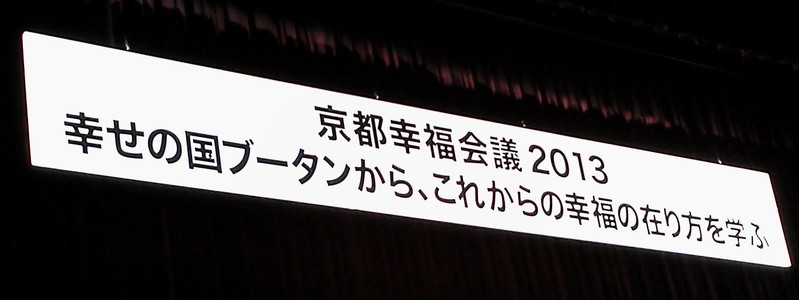
コメント