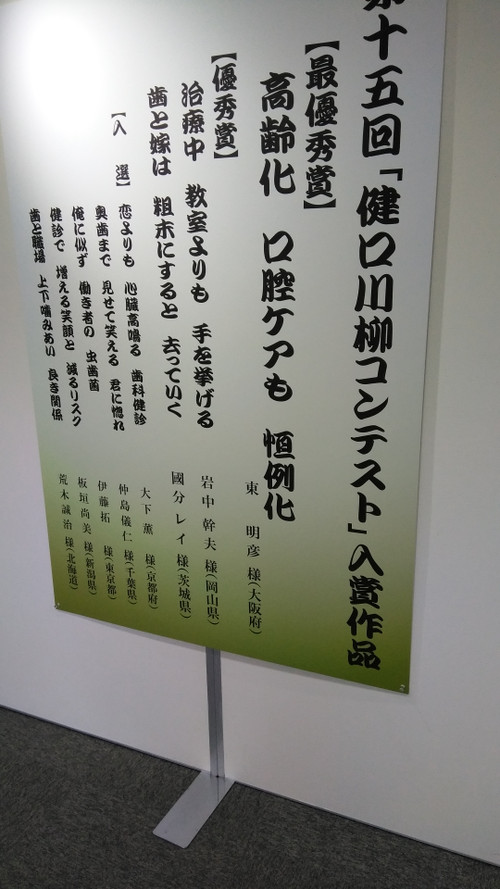ある研究者の「老人と若者の以外な関係」というコラムを目にした。研究者は、「心地よい街」をテーマに、ゼミ学生にワークショップでその課題を調査しているという。特に、ヨーロッパの建築家のクリストファー・アレグサンダー氏が提唱する「老人と若者の関係性」に注目し、若者の多くが、「老人」というファクターが、心地良い街を構成する大きな要素であることを自らの調査結果をもとに主張している。
研究者の調査で、若者が老人をなぜまちづくりの重要な要素としているかについて、①老人は気さくに話すことができる。②老人は落ち着きがあり。③老人がいると心が休まる。という理由を挙げている。そして、アレクサンダー氏のいう「老人とは老人を必要とするが、同時に若者も必要である。また若者も老人との接触を必要としている」の指摘を踏まえ今後の、まちづくりの方向を打ち出している。
現在、京都市は、京都駅東南部エリアにおいて、「若者と芸術のまちづくり」を理念としたまちづくりを進めようとしている。他文化力を都市の重要な要素としてまちづくりを創造しゆくことは時に叶ったものである。また次代を担う若者に、未来のまちづくりを託すことも反論はない。
しかし、重要なことは、東南部エリアのまちづくりの風景に、「老人」という視点はこれまでなかったものである。
多文化が共生してきた歴史的経緯は活かしてこそ意味があり、間違っても封印するようなことがあっては本末転倒のまちづくりとなる。