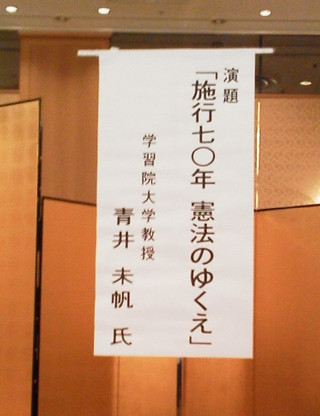代表質問(京都市会本会議)
京都市会11月定例会は11月29日、本会議場において各派代表制による一般質問が行われました。公明党市議団からは会派を代表し、青野仁志議員(中京区)、国本友利議員(左京区)が質問に立ちました。青野議員は、①伝統産業活性化に向けて今後の取組、②地域包括ケアシステム構築に向けた介護予防、認知症対策、③オリンピック、パラリンピック教育の推進、④元教業小学校跡利利用を契機とした二条城南部の活性化、について質疑を行いました。また、国本議員は、①大規模災害時における受援体制、②文化芸術による社会包摂の取組、③小中学校におけるプログラミング教育の推進、について質疑を行いました。その他、各会派からは、児童養護施設退所者支援、文化庁京都移転の対応、自転車対策、在宅医療と介護との連携強化、住宅宿泊事業法への対応、2020年住宅の省エネ全面義務化への対応、上下水道の防災危機管理体制などについて質疑がありました。
青野仁志議員の代表質問(全文)…aono20171129.pdfをダウンロード
国本友利議員の代表質問(全文)…kunimoto20171129.pdfをダウンロード